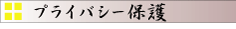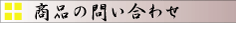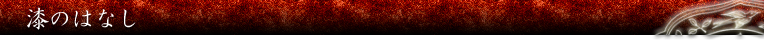


漆は、東南アジアに広く分布するウルシノキの樹液から作られます。
漆の木を植えてから10年から15年経ったものを
ゴムの木のように、傷をつけ漆の樹液を採取します。
漆の樹液を採取することを「漆かき」といい、
その職人さんを「掻き子さん」と呼びます。
掻き子さんは、山間を歩きながら、
葉を触るだけでもかぶれてしまうほどの
取り扱いの難しい困難な仕事をしています。
その為、現在、輪島では数人しかいないといわれています。
漆かきの時期は、6月~11月で、
一人の掻き子さんが約400本の木を回って漆を採取します。
漆の木は、傷をつけると、それを修復するかのように
特別な樹液をだします。これが漆の原料です。
樹液を採り終わった漆の木は切り倒して
新しい苗を植え、大切な漆の木が絶えないようにしています。
漆の主な成分はウルシオールというもので、
大腸菌などに対し抗菌作用があります。
完全に固まった漆は、酸やアルカリにも影響を受けず
永年お使いいただく食器はもちろん
代々継いでいく「御位牌」にも適しています。
近年、モダンな唐木の御位牌も増えてきましたが、
美麗にして耐久性のある漆塗りの御位牌は
今日も人気が衰えることなく作り続けられています。
漆の木を植えてから10年から15年経ったものを
ゴムの木のように、傷をつけ漆の樹液を採取します。
漆の樹液を採取することを「漆かき」といい、
その職人さんを「掻き子さん」と呼びます。
掻き子さんは、山間を歩きながら、
葉を触るだけでもかぶれてしまうほどの
取り扱いの難しい困難な仕事をしています。
その為、現在、輪島では数人しかいないといわれています。
漆かきの時期は、6月~11月で、
一人の掻き子さんが約400本の木を回って漆を採取します。
漆の木は、傷をつけると、それを修復するかのように
特別な樹液をだします。これが漆の原料です。
樹液を採り終わった漆の木は切り倒して
新しい苗を植え、大切な漆の木が絶えないようにしています。
漆の主な成分はウルシオールというもので、
大腸菌などに対し抗菌作用があります。
完全に固まった漆は、酸やアルカリにも影響を受けず
永年お使いいただく食器はもちろん
代々継いでいく「御位牌」にも適しています。
近年、モダンな唐木の御位牌も増えてきましたが、
美麗にして耐久性のある漆塗りの御位牌は
今日も人気が衰えることなく作り続けられています。
ウルシノキは、ウルシ科ウルシ族の落葉高木で
漆の語源は「麗し(うるわし)」とも
「潤し(うるおし)」ともいわれています
漆の語源は「麗し(うるわし)」とも
「潤し(うるおし)」ともいわれています
11月13日は「うるしの日」
平安時代、文徳天皇の第一皇子・惟喬親王(これたかしんのう)が
京都・嵐山の虚空蔵法輪寺にこもり祈願したところ
漆器製造法を虚空蔵菩薩から伝授されたという言い伝えがあることから
満願の日のこの日を「うるしの日」として、
虚空蔵法輪寺(別名うるし寺)で毎年法要(漆まつり)が行われています。
京都・嵐山の虚空蔵法輪寺にこもり祈願したところ
漆器製造法を虚空蔵菩薩から伝授されたという言い伝えがあることから
満願の日のこの日を「うるしの日」として、
虚空蔵法輪寺(別名うるし寺)で毎年法要(漆まつり)が行われています。
(c)2014 Riso Boeki Co.,Ltd. All Rights Reserved.
本サイトの画像・文章・写真等の著作権は 株式会社理想貿易 仏縁堂 に帰属しています。
本サイトに掲載されている画像・文章・写真等の無断使用・転用・転載・複製・改ざんは
各国の著作権法・各種条約・法律により禁止されています。
本サイトの画像・文章・写真等の著作権は 株式会社理想貿易 仏縁堂 に帰属しています。
本サイトに掲載されている画像・文章・写真等の無断使用・転用・転載・複製・改ざんは
各国の著作権法・各種条約・法律により禁止されています。




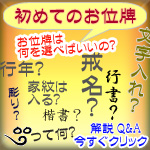
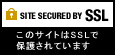
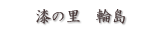
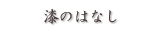
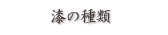
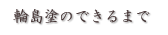
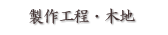
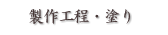
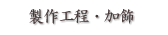
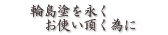


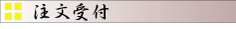
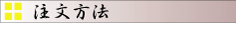
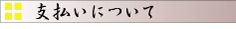
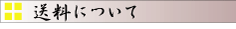
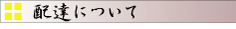

 弁護士法人
弁護士法人